更年期の女性に現れる不調や不快感は、女性ホルモンの分泌量減少で、自律神経の働きが不安定化(『更年期障害』)した影響もありますが、それとは別に、毎日の家庭や仕事のストレスや疲労などによって、自律神経に乱れ(『自律神経失調症』)が生じた影響もあります。
これは、自律神経が、身体を緊張させる“交感神経”と、身体をリラックスさせる“副交感神経”のバランスをとって、体調を維持しているので、更年期の「加齢による体力低下」、「日々の疲労や緊張」、「介護の疲れ」、「生活の変化に伴うストレス」などで自律神経のバランスが崩れると、頭痛、めまい、肩こり、腰痛、疲労感、倦怠感などを引き起こすからです。
この為、更年期の不調や不快感の改善には、自律神経の負担を減少させて、自律神経のバランスを回復させる事が必要なので、身体に蓄積した疲労や緊張をチェックして解消し、これにより、血液やリンパ液の流れを改善して敏感になっている身体の神経を和らげ、身体の調子(治る力)を上げていく事が必要です。
【 加齢による体力低下、精神的なストレスから 】
~ 女性ホルモンの分泌減少だけでなく ~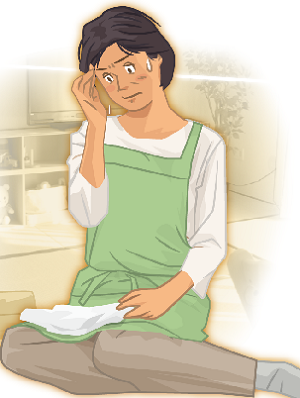
更年期の女性に現れる身体の不調や不快感の原因として、よく言われるのが、「女性ホルモンの分泌の急激な減少と、その影響による自律神経の乱れ(『更年期障害』)」です。
しかし、自律神経を乱す原因は、それだけでなく、更年期になると体力が弱くなっていたり、身体の機能が低下していたりするので、日々の疲労や緊張、家庭内のストレス、心の中に溜まった不満やモヤモヤ感なども、大きく影響しています。
これらによって、更に自律神経の負担が増すと、イライラ感や憂鬱感などが強まったり、気持がふさぎ込む事が多くなったりして、いろいろな心身症状(『自律神経失調症』)を引き起こすからです。
~ 更年期の自律神経失調症 ~
更年期に自律神経の負担が増して『自律神経失調症』を引き起こすと、不安に感じられるような理由がなくても、不安感が増したり、安心できなくなって気持ちが落ち着かなくなったりします。
例えば、「必要もないのに、不安を感じてしまう」、「負担感が強まる」、「心の落ち着きが無くなって、集中力が失われる」、「疲れ易くなって、無気力になる」、「日常生活に不安を感じる」、「いつも身体が緊張している」などです。
しかも、気が重くなったり、精神的に不安定になったりすると、心の中に溜まった不満やモヤモヤ感などを、自身で解消するのが難しくなるので、ますます、気持ちを安定させるのが難しくなります。
~ 気持ちの安定が難しくなると ~
これらによって、気持ちの安定が難しくなると、イライラ感や憂鬱感が急に強くなったり、いつまでも身体に残ったりします。
気持ちが不安定になると、神経が敏感になって心のコントロールできなくなり、急にイライラ感や憂鬱感が高まったり、イライラ感や憂鬱感が解消されなくなったりするからです。
この結果、「休んでも、しばらくすると、また、身体が重ダルイ感じになる」、「日中は何とかなるが、夕方になると疲労感や倦怠感で気力が落ちる」、「チョッとでも疲れを感じると、疲労感や緊張感をぶり返してしまう」などが起きるようになります。
【 更年期と上手く付き合うために 】
~ 一人で抱え込んでいると ~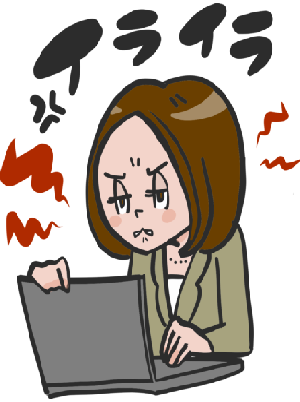
ところが、更年期の疲労感や倦怠感に悩まされても、「家族に不快な思いをさせたくない」とか、「やらないと、家事や仕事に支障が出る」と考えて、いつも通りに、仕事や家事を行うようになります。
しかし、ストレスや疲労は心身に蓄積するので、そのまま一人で我慢していると、自律神経への負担が大きくなっていきます。
この結果、身体の緊張が続いて、身体の血行が悪化してくると、「肩こり」、「腰痛」、「朝夕の関節痛」、「寝つきが悪い」、「体調の不良」などに悩まされたり、「汗をかきやすい」、「顔がほてる」などが起きたりします。
~ 改善できるものは改善して ~
このような心身の不調を緩和して、毎日を上手に過ごすには、改善できるものは改善して、体調を保つ自律神経の負担を少なくする事が大切です。
特に、運動不足やストレスなどで血行が悪化していると、身体の神経が敏感になって、自律神経のバランスを崩し易くなるので、対策方法として、身体の緊張を和らげて、血液やリンパ液の流れをスムーズにさせ、敏感になっている身体の神経を和らげる事が必要です。
この為、更年期の、血行と自律神経を安定化させて身体の機能を向上させる為に、食生活の注意や有酸素運動などの“身体のコンディショニング”が重要になります。
~ 有酸素運動 ~
中でも、軽いジョギングやウォーキング、水泳などの有酸素運動が、更年期の“身体のコンディショニング”として勧められています。
有酸素運動をする事で、血行が適度に促進される効果や、ストレス発散やリラックス効果が得られるからです。
更に、昼と夜の睡眠リズムを整えてグッスリ眠れるようにもなるので、自律神経の働きを安定させる効果もあります。
【 運動コンディショニングの難しさ 】
~ ウォーキング ~
特にウォーキングは、有酸素運動の中でも、更年期の症状改善に効果があると認められ、しかも手軽で、いつでもどこでも可能です。
しかし、ブラブラ歩きのウォーキングでは、更年期の症状改善の効果が期待できないので、50才代では速歩程度、40才代となるとジョギング以上の強さが必要とされます。
反対に、ウォーキングを、普段の体力以上にガンバッテ、長時間したり、ランニングのようにスピードを上げたりすると、運動した後になって、血管が収縮して血流が悪くなるので、「疲労が残る」、「血圧の変動が大きくなる」、「動悸がする」、「体調がかえって良くない」といった不調を起こして、逆効果になります。
~ 運動の目安 ~
また、更年期になると、運動する習慣が無くなっていたり、毎日の活動量が少なくなっていたりするので、普段の体調や身体の状態に合わせて、ウォーキングの運動量を調節をする事が大切です。
この為、更年期になって運動不足になっていたり、身体に不調を感じていたりすると、“身体のコンディショニング”としての運動を、「あまり抵抗感なく」、「どのような方法」で、「どのようにしたら良いか」などが問題になります。
特に、更年期に多い、頭痛、めまい、不眠、不安感、気分のうつ、イライラ感などの心身症状に悩まされていると、症状改善の為の“身体のコンディショニング”が難しくなります。
~ 身体の異常 ~
更に、更年期の症状に悩まされていると、ケガや病気と違って、不定愁訴と言われるように、「病気ではないが、身体の調子が悪い」と感じられる為に、“身体のコンディショニング”の具体的な対策が取りづらくなります。
この為、更年期の身体の不調を緩和したり解消させたりするには、血行の悪化箇所や、神経が敏感になって痛みを引き起こしている箇所を調べて確認し、それらを回復させる事が必要です。
しかし、自分で、気になる更年期の症状の原因が分からなかったり、身体の不調箇所を調べる事ができなかったり、不調箇所を改善する事ができなかったりするので、「更年期のコンディショニングを、どうしたらいいのか…?」という事になりがちです。
【 当院の、更年期の体調調整 】
~ 基礎的な回復から ~
当院は、このような更年期の疲労感や倦怠感の改善に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、体調や体質に合わせて身体の調子(治る力)を上げ、追い付かなくなっている身体の回復力を取り戻すようにしています。
更年期になると、加齢や運動不足などで、本人が思っている以上に基礎的な運動能力が弱っているので、「①身体が硬い」、「②関節の動きが悪い」、「③身体に左右差がある」、「④正座したり直立したりすると、身体を支える力が弱い」などが起きているからです。
これらの体力低下や身体の不調によって、姿勢の悪化や、「病気ではないけれど、何となく身体の調子が悪い」といった更年期の症状が起きます。
~ ツボ(反応点)の利用 ~
この為、当院では、身体のコワバリ箇所や血行悪化箇所の確認と、症状軽減の為に、マッサージ治療にツボ(反応点)治療を加えて、身体が本来持っている回復力を取り戻すようにしています。
これは、ツボが、身体の異常を知らせる箇所であり、病状を改善する箇所でもあるので、ツボ刺激によって筋肉の張りをほぐしていくと、内部から血行が改善され、酸素や栄養が身体に行き渡り、老廃物が排出される効果があるからです。
また、ツボの反応点を利用しているので、本人が気づいていない筋肉の疲労箇所やコワバリ箇所をチェックして解消させたり、血行が悪化している箇所を回復させたりするのに、効果があります。
~ 問診や触診にウエイトを置いて ~
また、ツボ(反応点)を利用したマッサージ治療で、筋肉の緊張をほぐして、血行改善を行うと、血行悪化で刺激された神経の興奮を鎮める効果があります。
この効果から、更年期の「肩がこる」、「冷える」、「ダルイ」といった症状も、「筋肉のコワバリ」、「血行の悪化」、「神経の異常な高ぶり」などが関係しているので、ツボ(反応点)を利用したマッサージ治療が症状の改善に適している上に、副作用が少なく、かつ安全性の高い治療になっています。
当院は問診や触診にウエイトを置いて、それぞれの症状、一人ひとりに適したツボを探し出し、手当(コンディショニング)を行っているので、身体の回復力を取り戻すだけでなく、気分をリフレッシュさせる効果もあります。
~ 身体のコンディショニング ~
更年期の体調改善に「“身体のコンディショニング”が必要」と分かっていても、「体調も気分もすぐれないのに、運動する気が無い」、あるいは、「運動なんて」とか、「忙しくて時間が無い」、という人が多くなっています。
当院は、ツボ刺激を利用したマッサージ治療で、慢性化した疲労や緊張などを解消して血行を改善し、体調の改善を行っているので、更年期の女性に現れる身体の不調や不快感の“身体のコンディショニング”にも適しています。
マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や、不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)

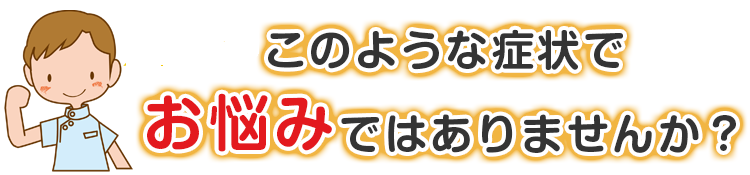

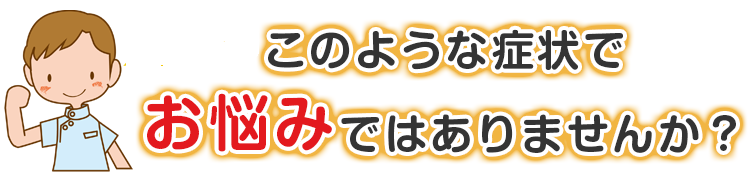




マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)

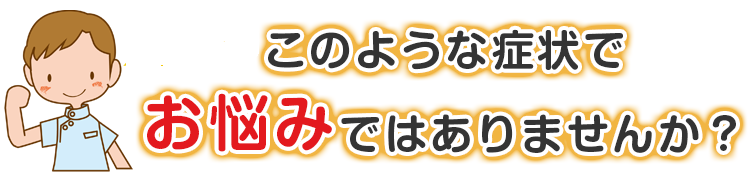
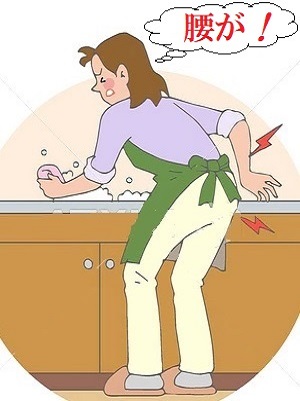



マッサージ専門【ファミリー治療院】-2.jpg)

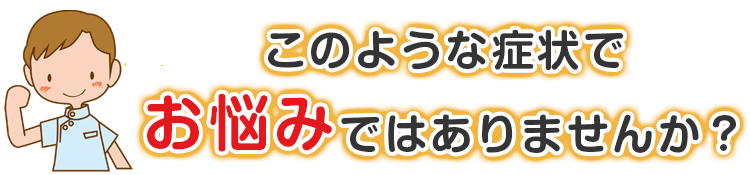


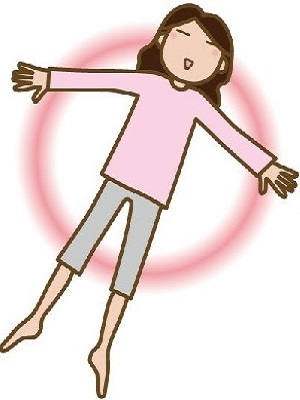

マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)





