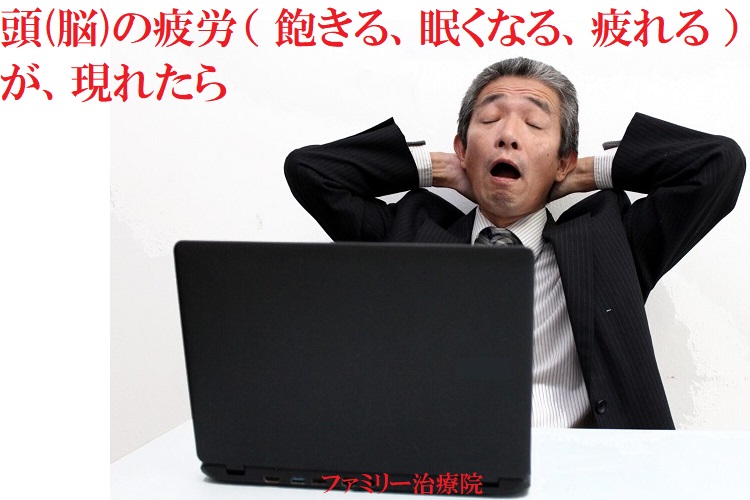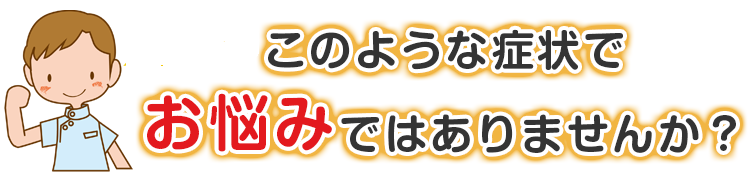仕事やストレスなどで頭が疲れてくると、「飽きる」、「眠くなる」、「疲れる」などの“頭の疲労サイン”が現れますが、その状態が毎日続くと、日が経つうちに身体に不調が起き始め、長引くと、休みをとっても、なかなか身体の不調が回復しなくなります。
これは、心臓や胃腸の動きや、体温、血圧、発汗などの調節を、脳内の自律神経が行っているので、仕事やストレスなどで脳の働きがオーバーワークになると、体調を保つ自律神経の働きが低下し、追い付かなくなってくるからです。
この為、「飽きる」、「眠くなる」、「疲れる」などの“頭の疲労サイン”が現れたら、身体からの“アラームサイン”と考えて、心身を休ませるだけでなく、健康状態に取り戻す為に、脳の疲労を回復させると、身体に生じた不調を解消する事が大切です。
【 頭の疲労サイン 】
~ 頭が疲労してくると ~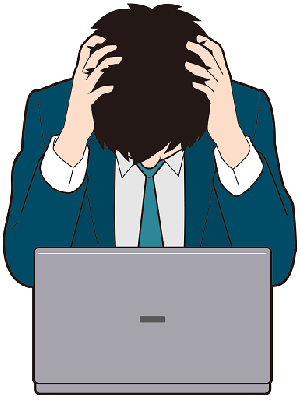
会社の仕事や人間関係、あるいは、プライベートなどで、ストレスを感じたり悩まされたりして、頭が休まらなくなってくると“頭の疲労サイン”が現れて、ミスを起こし易くなったり、根気や集中力が続かなくなったり、感情が安定しなくなったりします。
ストレスや悩みなどで、頭が疲労してくると、脳内の情報伝達や整理整頓がキチンとできなくなるので、「頭がボンヤリしてくる」、「考えがまとまらない」、「頭の中がモヤモヤする」、「人の話についていけなくなる」などが起き、ミスを起こし易くなるからです。
更に、頭の疲労によって、体調を保つ機能に混乱が生じて、根気や集中力が続かなくなったり、理解力や判断力が低下してくるので、感情面が優位になり感情が安定しなくなったりします。
~ 頭の疲労サイン ~
これらの“頭の疲労サイン”で、最初に現れるのが『飽きる』で、続ける気力が無くなって、「もう、これ以上続けたくない!」、「面倒くさい」、「イヤになる」などを感じて、途中で辞めたくなります。
それでも、何とかガンバって続けていると、『眠くなる』が現れて、「頭がボーっとする」、「ウツラウツラとしてしまう」、「目がショボショボする」などが起き、眠気によって脳の活動を休ませようとします。
それでもなお、ガンバリ続けると、『疲れる』が現れ、「頭がズンと重くなる」、「あくびが出る」、「何もする気が起きない」などが起き、「強く疲れを感じて、これ以上続けるのが無理」といった状態になり、半ば強制的に休まざるをえなくなります。
~ それでも続けていると ~
このような“頭の疲労サイン”が現れても、「一時的な疲労」とか「寝れば治る」と思って、そのまま続けていると、日が経つうちに、次第に、身体にいろいろな不調が起き、そして、感情のコントロールも困難になります。
脳は神経を通じて心身を管理しているので、脳が疲れると、自律神経がオーバーワークの状態になって、安定的に心身を維持する事ができなくなるからです。
この結果、「いつも、身体がダルイ」、「頭がボーッとして、物事の判断がつきにくい」、「能率が悪くなった」、「朝になっても寝入ったまま、起きられない」などや、感情的にも、「些細な事で、感情が不安定になる」、「イライラしてくる」などが生じます。
【 脳と首の関係 】
~ 頭の付け根、肩、肩甲骨などの凝りや痛み ~
また、「飽きる」、「眠くなる」、「疲れる」などの“頭の疲労サイン”が現れてくると、後頭部や、頭の付け根、肩、肩甲骨などに、“凝り”や“痛み”が生じます。
これは、姿勢を維持する筋肉の疲労だけでなく、それによって、筋肉のコワバリ、背中のコワバリによる血行悪化、姿勢の悪化、作業上の左右の筋肉の不均衡、骨盤の高さの左右差などが生じるので、後頭部や、頭の付け根、肩、肩甲骨などに、身体的負荷や動作時の負担が大きくなるからです。
しかも、これらの緊張した筋肉が、首から背骨沿いに通っている自律神経を圧迫すると、自律神経の通り道になっている後頭部や、頭の付け根、肩、肩甲骨付近の筋肉のコワバリが強まって血行が悪化し、“凝り”や“痛み”を悪化させます。
~ 脳の重要な通り道 ~
特に首は、脳に通じる神経や血管の“重要な通り道”になっている上に、首の上半分は重要な神経や血管が集中しています。
この為『首の上半分は、脳の下側の延長』と言われるように、首と脳の機能が絡み合った状態になっています。
ところが、頭の付け根、肩、肩甲骨などが疲労したり緊張が続いたりして、首の筋肉のコワバリが強まると、脳に通じる神経や血管を圧迫したり、血行を悪化させたりして、脳に疲労や頭痛を起こします。
~ 首と脳の疲労が増すと ~
また、首や脳が疲労してくると、自律神経のコントロール力も低下するので、交感神経が高まって神経が敏感になり、チョッとした疲労や緊張、あるいは、気候の変化でも、身体の筋肉や血管が収縮し、血行を悪化させます。
これにより、、「頭痛」や、「頭重感」を引き起こしたり、「身体がダルク、不快な感じがする」、「気持ちがすっきりしない」、「不安を感じる」、「イライラする」などの体調を悪化させたりします。
更に、血行悪化で筋肉内に疲労物質が溜まったり、それによって神経が敏感に反応する状態になったりすると、痛みの調整がうまく働かなくなるので、解消が困難になったり、繰り返したりします。
【 脳の疲労の判断 】
~ 疲労と疲労感 ~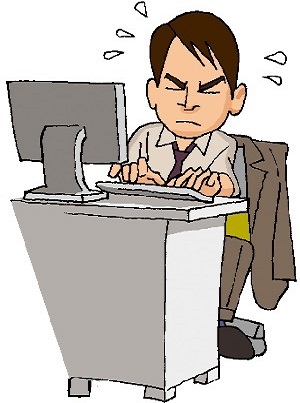
ところが、仕事やストレスなどで、「飽きる」、「眠くなる」、「疲れる」などの“頭の疲労サイン”が現れても、気付きにくくなっている事があります。
例えば、仕事に追われていたり、やりがい感や使命感などが大きくなっていたりすると、“頭の疲労サイン”が現れても、「たいした事はないだろう」と過小評価したり、あるいは、「身体を休めれば回復する」とか、「ゆっくりと、お風呂に入れば大丈夫」と都合良く考えたりします。
これは、心身の負担が大きくなって身体の能力が低下した状態を“疲労”と言いますが、“疲労感”は「疲れている」という感覚なので、心身に蓄積した疲労が、必ずしも疲労感として現れるとは限らないからです。
~ 疲労の判断 ~
この事から、「飽きる」、「眠くなる」、「疲れる」などの“頭の疲労サイン”が現れたら、首や首周辺のコワバリをチェックしてみる事が、大きな判断材料になります。
首や首周辺に凝りや痛みを感じる状態になっていると、首の筋肉のコワバリが脳への血行を悪化させて自律神経を乱し、体調を保てなくなっている可能性が高いからです。
特に、後頭部の圧迫感や頭重感に悩まされる場合は、首コリや肩コリが悪化していたり、慢性化していたりする事が多くなっているので、体調悪化に結び付き易くなります。
~ 上半身の疲労解消も ~
また、脳の疲労で、自律神経の働きが低下すると、疲労や不調を回復させる機能が低下してくるので、「家でボーっと休む」、「栄養を十分に摂る」だけでは、心身の疲労が解消されず、仕事に取り掛かると、すぐに疲労がぶり返したり、いつまでも疲労が続く状態になったりします。
しかも、デスクワークなどで、一日中、前かがみ姿勢になっていると、肩や背中の筋肉がコワバッテ、呼吸が浅くなったり、首の筋肉のコワバッテ、脳の血行が悪化したりします。
特に、後頭部や首、背中などに“凝り”や“痛み”が生じていると、脳と身体の疲労に大きく影響を与えたり、神経や血管が集中している首の上半分に影響を及ぼして、頭痛、ダルサ、めまい、肩こり、胃腸障害などを引き起こしたりします。
【 当院の、頭(脳)の疲労解消 】
~ 脳の疲労解消 ~
仕事やストレスなどで頭が疲れてくると、心身の疲労や緊張が増すだけでなく、身体に不調が起きたり、身体の回復力が低下したりするので、身体の緊張感や疲労感を和らげて、身体の回復力を取り戻す事が大切です。
更に首は、脳の“重要な通り道”になっているので、後頭部や首周辺の筋肉の疲労を解消させて、脳への血流を活発化させ、脳の疲労の解消を促し、自律神経の働きを回復させる事も必要です。
当院では、東洋医療をベースとしたマッサージ治療とツボ治療で、首・肩・背中などの柔軟性を回復させて、脳への血行を促し、これにより“頭の疲労サイン”の「最近なかなか疲れが取れない」、「何だか身体がダルイ」、「眠れない」、「集中できない」などの解消を行っています。
~ 首のツボ利用 ~
当院が、ツボ治療を併用しているのは、ツボが神経や血管が集まっている箇所なので、反応が強く現れた首のツボに適切な刺激を与えると、ツボ刺激に反応して、首周辺の痛みや違和感を減少させたり、首の筋肉内の血流を改善したりするからです。
しかも、首は、脳の働きを活性化するツボがあるので、脳の疲労を回復させる為に、昔から利用されている、首の後ろ側にある『天柱』と『風池』と呼ばれる2つのツボを治療に利用しています。
この『天柱』と『風池』のツボに刺激を与えると、首の後ろ側の筋肉のコワバリが緩和して、血流が回復し、脳の血行が改善されてくるので、これによって体調を整える神経が働くようになり、リラックス効果も期待できます。
~ 肩や背中のシコリやコワバリの解消 ~
更に、体調の回復を高める為に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、肩や背中のシコリやコワバリを解消させ、血行の回復を行っています。
東洋医療をベースにしたマッサージ治療は、「筋肉の弾力性や柔軟性を高める」、「血行やリンパの流れを良くする」などの作用だけでなく、これらによって「敏感になっている神経の回復」作用もあるので、体調や症状に合わせて身体の調子(治る力)を上げていく事ができます。
これによって、身体の疲労解消を高め、回復力を取り戻す事ができます。
~ なかなか回復しない場合には ~
休みや栄養をとっても、身体の疲労や不調がなかなか回復しない場合は、脳の疲労によって身体の回復が追いつかず、疲れ・痛み・不調が続いている事があります。
当院では、このような疲れ・痛み・不調に対して、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、首周囲や後頭部の緊張を解消させて、脳の血流を改善し、体調を保つ自律神経の働きを高め、身体の疲労感や緊張感の解消を行っています。
マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する疲労やだるさなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)