【(症例)身体の不調や、不快感 】
季節に関わらず、お腹の冷えに悩まされている人は意外と多く、「下痢や便秘が続く」、「お腹にガスが溜まって辛い」、「お腹をこわし易い」、「おしっこが近い」、「疲れ易く、頭重感もする」などの悩みを、よく聞きます。
しかも、お腹が冷えると、“体温”と“身体の水分調整”の働きが乱れて、「チョット身体を動かすと、すぐに汗をかく」、「暖かい食べ物を食べると、額から大汗が出る」など、思いがけないような“汗かき”や“暑がり”になります。
このような、お腹の冷えを『内臓型冷え性』と言い、内蔵の冷えによって、「身体がダルイ」、「肩がこる」、「疲れが残る」、「食欲がない」、「眠れない」、「イライラする」なども起きるので、お腹を温めるだけでなく、体調の改善を行い、自律神経のバランスを整える事が大切です。
【 内臓型冷え性の原因 】
~ 内臓型冷え性 ~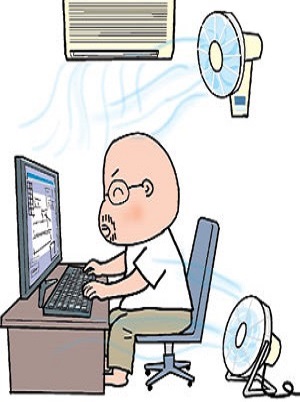
一日中のほとんどを、座りっぱなしだったり、ストレスフルであったりすると、気付かないうちに“体内”の筋肉の発熱と血液を送る働きが低下してくるので、内蔵に冷えが生じます。
内蔵に冷えが生じると、胃腸の機能が低下したり、食べ物の消化や吸収がスムーズに行われなくなったりするだけでなく、腸は“免疫の要”になっているので、感染症に罹患し易くなって、思わぬトラブルを招きます。
このように、お腹の冷えが一時的ではなく、慢性的にお腹が冷えて、症状が長引く状態を『内臓型冷え性』と言います。
~ オフィス環境 ~
特に、デスクワークをするオフィスは、いつも涼しく、そして快適に感じられるように、室温を低めに設定されているので、血管が収縮して血行が弱くなり、内蔵に冷えが生じ易くなります。
しかも、オフィスでの仕事は身体を動かす事が少ないので、身体の発熱量が少なくなる上に、仕事や人間関係などの緊張や疲労で、血液を送る働きがますます悪くなります。
この結果、オフィスで仕事をしていると、快適に感じられても、低めの室温、身体の発熱量低下、血行悪化などで、内蔵が冷える『内臓型冷え性』が起き易くなります。
~ 血管の収縮反応がニブクなっていると ~
ところが、慢性的なストレスや長期間の運動不足で血管の収縮反応がニブクなっていたり、あるいは、生まれつきの体質で血管の収縮反応がニブクなっていたりすると、手足や身体の表面の血行が保たれるので、内蔵が冷えても、手足や身体の表面が温かく感じるので、内蔵の冷えに気付かなくなります。
これを『隠れ冷え性』と言い、一見、元気そうな若い男性でも、運動不足やストレスなどが続くと『隠れ冷え性』が起き易くなります。
しかし、内臓が冷えで、胃や腸の働きが悪くなるので、「頻繁にトイレに行きたくなる」、「腹痛」、「下痢」などを繰り返すようになります。
【 身体への影響 】
~ 体調の低下 ~
『内臓型冷え性』は胃や腸の働きが悪化して、下痢や便秘、下腹部の不快感や痛みなどを繰り返しますが、腰周辺の血行が悪化し筋肉がコワバッテくるので、腰にダルサや痛みを感じる事が多くなります。
更に、お腹や腰の筋肉のコワバリが続いて、身体全体の血液循環が悪くなると、「身体の調子が、何となく悪い」といった状態になり、慢性的な肩こりや頭痛、腰痛などにも悩まされます。
しかも、腸は“免疫の要”になっているんで、内臓の働きが低下すると、身体の代謝や免疫力などが低下してくるので、「身体が疲れる」、「体調の悪化が続く」、「食欲がない」などが起きます。
~ 精神面の不調 ~
また『内臓型冷え性』で、身体の代謝や免疫力などが低下し、体調を維持しづらくなると、精神的に、「以前と違って、最近、集中力が続かない」、「気力が低下して、活動的になれない」、「イライラする」、「頭が重い」、「眠れない」などが起きます。
これにより、集中力が落ちたり、判断力が無くなったり、ヤル気が続かなくなったりします。
しかも、「身体の血行悪化→肩こり・頭痛・腰痛→身体や精神面の不調→身体の血行悪化」、といった悪循環になります。
~ 見た目や体型の変化 ~
更に、不健康そうな顔つきになったり、体型が崩れて太ったりします。
『内臓型冷え性』になって、身体の血液循環が悪化してくると、顔の血行やリンパ液の流れも悪くなるので、「疲れたような顔つき」になったり、「顔つきが不健康そう」にむくんできたりするからです。
そして、体型も、内臓の体温低下によって、今迄のように内臓脂肪を燃焼できなくなるので、内臓に脂肪が溜まり、お腹やお尻が太るようになります。
【 特徴的な、汗かきと暑がり 】
~ 体内に余分な水分が溜まる為に ~
また『内臓型冷え性』が続くと、暑さに敏感になって、汗かきや、暑がりになります。
内臓の冷えで自律神経の働きが乱れると、内臓の血液の流れが悪くなり、血液中の水分が内蔵に浸透して“余分な水分”が溜まるので、少しでも暑さを感じると“余分な水分”を排出する働きが強まり、汗をかくようになるからです。
この為『内臓型冷え性』が続くと、暖かい食べ物を食べたり、いつもより身体を動かして体温が上昇したりすると、“余分な水分”を排出する働きが強まり、大汗をかくようになります。
~ 太ってメタボになると ~
そして、加齢や運動不足などで太り、メタボ体型になると、余計に、大汗をかく傾向が強まります。
脂肪は一度冷えると温まりにくい性質がある上に、内臓に脂肪が溜まると内臓を冷やしてしまうので、内蔵に脂肪が付いてメタボ体型になると、内蔵を冷やす“余分な水分”が溜まると、体内から“余分な水分”を排出する働きが一層強まるからです。
しかも、内が冷えると“体温”と“身体の水分”を調整する働きが、うまく働かなくなるので、体温が上昇すると、急激に大汗をかくようになります。
~ 汗かきや暑がりであっても ~
このように、一見、体質的な汗かきや暑がりのようであっても、実際は『内臓型冷え性』で、汗かきや暑がりになる事があります。
しかも本人は、暑がり、汗かき、のぼせ、などを強く感じているので、『内臓型冷え性』とは思っていません。
しかし『内臓型冷え性』の為に、涼しい所にいると、ひどく寒さを感じたり、お腹が痛くなったりします。
【 内臓型冷え性の、チェック法 】
~ お腹を触って ~
『内臓型冷え性』は、簡単に自分でチェックできます。
生命維持の為に、内蔵の温度は皮膚温よりも0.5℃から1℃ほど高く、37℃前後に保たれているので、通常ならば、お腹は温かいはずです。
しかし、肌寒い気温でもないのに、お腹を触ってみると「ヒンヤリ」と冷たく感じたり、「起床時に、脇よりもお腹の温度が低い」と感じたりする場合は、内臓の温度が低くなっている事が考えられます。
~ 手が冷たい ~
また『内臓型冷え性』になっていると、人と握手すると「手が冷たい!」と言われます。
内臓が冷えていると、身体の表面の体温も低くなり、一般的な平熱とされている36.5度に満たなくなるからです。
しかし、本人は自覚症状が無いので、自分の体温が低くなっている事に気付きません。
~ 病院の診断 ~
西洋医学では、「冷え」とは客観的な体温の低下を意味しますが、病院で『内臓型冷え性』を診てもらっても、体温を測っても特に低くなく、血液や内臓を調べても異常がありません。
この為、『自律神経失調症』の一種と診断され、身体の不調は「冷えに敏感」による為とみなされます。
この結果、治療は、自律神経のバランスを整える事を目的とした薬を処方され、そして、お腹が冷えて下痢をしている場合には整腸剤、身体に痛みを感じていれば鎮痛薬を処方されます。
【 当院の、冷え治療 】
~ マッサージ治療にツボ治療を加えて ~
『内臓型冷え性』対策として、「お腹を温める」、「身体を温める食べ物をとる」、「軽い運動やストレッチ」などが紹介されています。
しかし『内臓型冷え性』は、冷えの改善だけでなく、運動不足や加齢などで筋肉の働きが低下していたり、ストレスや疲れが溜まって影響していたりするので、身体の疲労と緊張の改善や、体調を整えて自律神経の負担を少なくする事が必要です。
この為、当院では、東洋医療をベースにしたマッサージ治療にツボ治療を加えて、身体の血行を回復させ、体調の改善を行っています。
~ 神経や血管が集まっているツボ ~
ツボ治療を加えているのは、ツボに神経や血管が集まっているので、冷えの症状や体調に合わせてツボを刺激すると、冷えで敏感になっている神経が和らいで、内臓の血行が改善するからです。
例えば、下半身の血行をマッサージ治療にツボ治療を加えて高めると、腰の「ダルサ」、「疲れ」などが解消されてくると共に、内臓の血流が回復してくるので、「お腹が張って苦しい」、「お腹がゴロゴロする」、「お腹が重苦しい」などの、不快感が緩和します。
しかも、ツボは、身体に不調があると、関係する特定のツボに痛みや硬さとなって現れ、身体に異常が起きている事を知らせてくれるので、『隠れ冷え性』の治療箇所を探すのに、重要な“手がかり”になります。
~ 中高年の体調改善に ~
また、中高年になると、ストレスや疲労の蓄積、血液の循環調整機能の低下、運動不足などで、内臓の冷えが起き易くなります。
この為、ツボ治療とマッサージ治療で、①血行やリンパの流れを良くする、②筋肉の弾力性や柔軟性を高める、③神経の興奮を鎮める(痛みの改善)、などを行うと、これによって筋肉の働きが回復して、活性化するようになります。
これによって、身体の熱を作る力が高まり、温められた血液が身体の隅々まで運ばれるようになると、身体の調子(治る力)が高まり、体調が回復してくるので、『内臓型冷え性』による身体の不調の解消になります。
~ 血行改善や体調の回復に ~
『内臓型冷え性』は、ストレスや疲労の蓄積、運動不足、血液循環の低下、などが主な原因になっているので、身体のチェックと、体調の改善によって、身体の血行を回復させる事が大切です。
当院は、身体の冷えの改善に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療にツボ治療を加えて、疲れ易さや不快感となって現れた箇所を確認し、血行の改善や体調の回復を行っています。
マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や、不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-3.jpg)
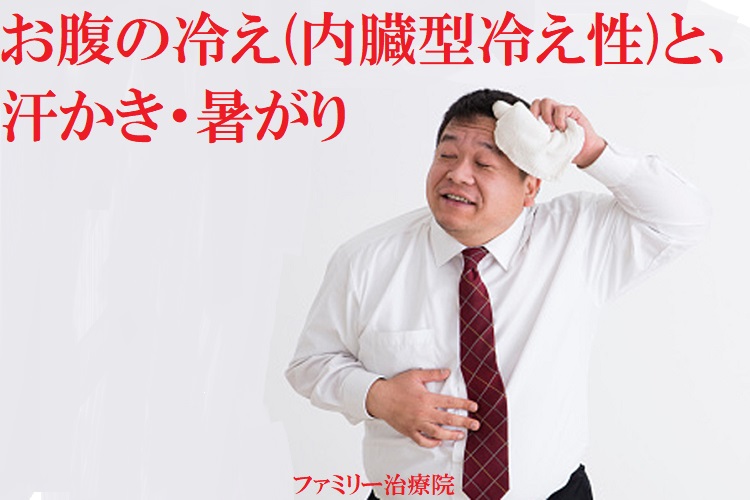
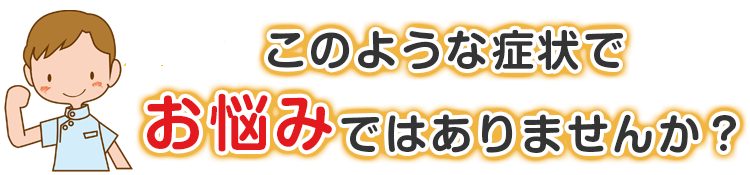

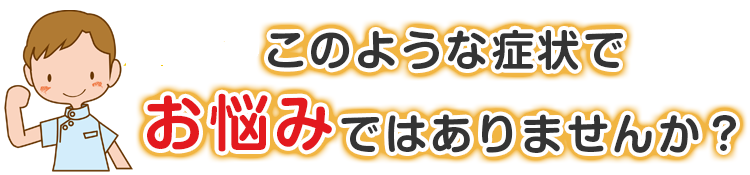




マッサージ専門【ファミリー治療院】-6.jpg)





