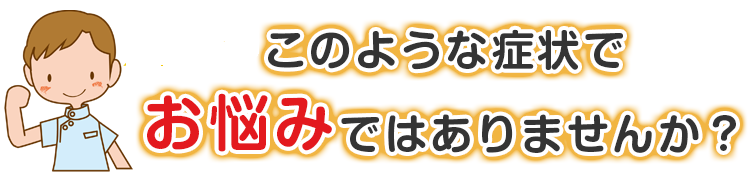『変形性膝関節症』は、膝関節の軟骨がすり減り減って炎症が生じ、膝が腫れたり痛んだりする病気ですが、もともとの原因は、「膝周りの筋力低下」、「肥満による体重増加」、「姿勢悪化による膝への負担増」などで、膝関節を支える筋肉の安定性が失われた為です。
この為『変形性膝関節症』は、いきなり膝の軟骨がすり減るのではなく、その前に、膝の筋肉から「コワバリ感」や「違和感」などが起きるので、この『変形性膝関節症』の“前ぶれ”のうちに、脚と腰の疲労とコワバリを解消させて、膝周辺の筋力バランスを回復させ、膝関節にかかる負担を減らす事が大切です。
このような膝関節のケアに、昔から筋肉や血行の改善を行っている東洋医療をベースにしたマッサージ治療を利用すると、腰や脚の筋肉の弾力性や柔軟性を回復させる効果で、膝関節のかみ合わせが改善され、変形性膝関節症を抑制する効果があります。
【 膝周辺の筋肉や靭帯のコワバリ 】
~ 体重の何倍もの負荷 ~
普段、何気なく、立つ、歩く、座るなどの動作を行っていますが、これらの動作や姿勢をスムーズに行うには、膝に、体重の何倍もの負荷がかかっています。
例えば、膝関節に、歩くたびに体重の2~3倍、階段を降りる時には体重の約3.5倍、走っている時には体重の4~5倍もの負荷がかかるので、体重50キロの女性の場合は、膝に、歩くたびに100~150kg、階段下りでは約175kg、そして走ると200~250kgの負荷がかかります。
膝の筋肉や膝関節を覆っている靭帯は、体重の何倍もの負荷を和らげる為に、重要なクッション役を果たしています。
~ 膝が弱ったりバランスが崩れたり ~
ところが、膝周りの筋肉や靭帯が、運動不足や加齢で弱ったり、体重が増えて負担が増したり、O脚で膝の内側に体重がかかり続けたりすると、膝関節のクッション役を果たせなくなり、膝関節のかみ合わせが悪くなって、関節の軟骨が傷付いたり、すり減ったりして、変形性膝関節症を引き起こします。
このように、変形性膝関節症は、膝周囲の筋肉が弱ったり、筋力バランスが崩れたりした事から起きるので、膝関節の軟骨が、ある日突然、いきなり、すり減ったり、傷ついたりする事はありません。
変形性膝関節症が起きる前は、膝周辺の筋肉や靭帯に、今までに無いような負担がかかり続けるので、膝に「コワバリ感」や「違和感」などの自覚症状が、症状の“前ぶれ”として現れます。
~ 膝の異常サイン ~
変形性膝関節症の兆候として、よく言われるのが、“立ち上がり”や“階段の上り下り”した時の、膝の内側の「コワバリ感」や「違和感」ですが、これ以外にも、「朝起きると、膝関節に痛みを感じる」、「膝の内側が突っ張る」などや、立っていたり歩いていたりすると、「膝がコワバッテ、動かしづらい」と感じる事もあります。
しかし、初めの頃は、動作の開始時に、膝に「コワバリ感」や「違和感」が起きても、自然と無くなってくるので、「一時的な痛みだろう」とか、「年齢や体力が弱った為だろう」と思いがちです。
しかし、膝の痛みが無くなっても、動作のたびに膝にコワバリを感じたり、痛みを感じたりするのは、膝の筋肉や靭帯に異常が起き始めたサインなので、脚と腰の状態をチェックして、疲労とコワバリを解消させて、膝周辺の筋力バランスを回復させる事が大切です。
【 変形性膝関節症のチェック法 】
~ 膝が伸び切らない ~
膝の内側の「コワバリ感」や「違和感」が気になった時のチェック方法として、次のような確認方法があります。
一番簡単なのが、座って、膝を床に付けるように脚を延ばしてみる方法で、「膝が伸び切らない」場合は、膝裏の筋肉が強くコワバッテいる事が考えられるので、これにより、膝関節のかみ合わせが悪くなっている可能性があります。
特に、膝裏にテレビのリモコンを差し込んで、スーッと入ってしまう場合は、膝裏が2cm以上床から浮いた状態なので、かなり膝周辺の筋肉や靭帯のコワバリが強まっている状態です。
~ 膝の特徴的な違和感 ~
また、膝裏の筋肉や靭帯のコワバリが強まると、膝裏にコワバリ感や違和感が生じるので、これらを確認してみる事も必要です。
例えば、「立った時に、膝の後ろに突っ張り感がある」、「正座すると、膝に何かが挟まったように感じる」、「3分以上正座すると、膝が辛くなる」、などです。
これらの違和感がある場合は、膝周りの筋肉や靭帯の力が弱ったり、膝の筋肉のコワバリが強まったり、これらで膝の筋力バランスが崩れていたりしている事が考えられ、更に、脚全体にコワバリが拡がっている事も考えられます。
~ 膝関節の、かみ合わせ悪化 ~
膝の状態をチェックして、このような膝周辺の筋肉や靭帯のコワバリ状態や違和感がある場合は、膝関節の前後左右の筋肉バランスが崩れて、膝関節のかみ合わせが悪くなっている事が考えられます。
特に、膝に“階段昇降時の痛み”を感じる場合は、初期の『変形性膝関節症』を特定する“特異的な痛み”とされるので、変形性膝関節症の初期症状が始まっている可能性があります。
日本人の女性は、8~9割がO脚気味なので、膝周辺のコワバリ感や違和感を何度も気付かされる場合は、O脚が進んで、膝の関節のかみ合わせが悪くなり、本格的な変形性膝関節症へと進んでしまう事があります。
【 症状の悪化 】
~ そのままにしていると ~
また、膝周辺の筋肉だけでなく、加齢や運動不足などで、腰・骨盤・股関節・足首などを支えている筋肉が弱ると、立ったり、歩いたり、座ったりなどの日常動作をするたびに、膝に大きな負担がかかります。
しかも、中高年になって運動不足が続いていたり、体重が増えたりしていると、動作や姿勢を保っている膝の筋肉負担が大きくなります。
この為、ジッと立っているだけでも膝に負担がかかり続けるので、膝周辺の筋肉や靭帯に大きな負担がかかり続けたり、膝周辺の筋力がアンバランスになっていたりすると、膝関節のかみ合わせが悪くなり、膝関節の軟骨に不自然な負荷がかかり続けて、軟骨が傷ついたり、すり減ったりする状態になります。
~ 膝関節の動作時の痛み ~
そして、膝の軟骨が傷んだり、すり減ったりしてくると、チョットした事でも、骨の神経が刺激されて、膝の内部から痛みが起きるようになります。
この結果、「階段を降りると、膝の内側が痛む」、「起床後、身体を動かし始めた時に、膝に痛みを感じる」、「歩き出すたびに、膝がズキズキと痛む」などが起きます。
また、動作時の痛みだけでなく、ジッとしていても、「膝が、重くて動かしにくい」、「膝関節から鈍い痛みを感じる」、などを感じるようになります。
~ 膝の筋肉のコワバリによる血行悪化から ~
更に、膝の筋肉コワバリが強まって膝の血管の弾力性が失われると、血行の悪化が慢性化するので、膝の筋肉からジンジンとする痛みがしたり、いつまでも痛みが続いたりします。
そして、「膝の内側が疼(うず)くように痛む」、「膝の内側の少し下を押すと痛い」、「シップを貼ると楽になるけど、しばらくすると膝の内側が痛くなる」なども起きてきます。
また、膝の関節が動かしづらくなると、腰や股関節にも影響して痛みが起きるようになったり、あるいは、下半身の血行悪化で全身の血液循環も悪くなってくると、身体全体の疲労感やダルサなどで悩まされたりします。
【 当院の、膝治療 】
~ 変形性膝関節症の初期症状に対して ~
変形性膝関節症は、膝周りの筋肉や靭帯が弱ったり、負担が大きくなったりするだけでなく、下半身の筋力バランスの不安定化でも引き起こされます。
この為、膝周囲だけでなく、腰や脚などの筋肉をチェックして、下半身の筋力バランスを改善すると、膝周囲の筋肉や靭帯の負荷が減り、膝関節のかみ合わせを改善する効果や、膝の敏感になっている神経が和らいで、痛みを緩和する効果があります。
当院では、変形性膝関節症の初期症状の膝の内側の「筋肉のコワバリ」や「違和感」などに対して、東洋医療をベースにしたマッサージ治療にツボ治療を加えて、腰や脚の筋肉疲労や緊張の解消と、症状の改善を行っています。
~ ツボの利用 ~
変形性膝関節症の改善にツボ治療のメリットとして、ツボに神経や血管が集まっているので、身体に不調が生じると、関係する特定のツボに痛みや硬さが現れて、身体に異常が起きている事を知らせてくれる事と、反応が現れたツボに刺激を与えると、その刺激に反応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があるからです。
しかも、腰や脚に、昔から使われている有効なツボがあるので、これらのツボを利用する事で、下半身の筋肉のコワバリやシコリが解消され易くなり、膝周りの筋肉の不自然な負荷を減少する事ができます。
このような効果から、当院では、変形性膝関節症の初期症状に対して、マッサージ治療にツボ治療を加えて、下半身全体の柔軟性を回復させて、悪化している血流を改善し、膝の痛みの減少と、膝関節の動ける範囲(可動域)を回復させ、膝関節の安定を図っています。
~ 腫れ(むくみ)の回復 ~
また、下半身の血液やリンパ液の流れを促進させ、腫れ(むくみ)の解消も行っています。
『変形性膝関節症』は、腰や脚の筋肉のコワバリから、血液やリンパ液の流れが悪くなって、腫れができるだけでなく、腫れ(むくみ)ができると老廃物が溜まり易い状態になり、神経を刺激して、違和感や痛みが起き易くなるからです。
この為、マッサージ治療にツボ治療を加えて、血液やリンパ液の流れを活発にすると、体内の老廃物の排出が進み、痛みが減少する効果だけでなく、コワバッテいる筋肉の回復効果が大きくなります。
~ 痛みや無理が無いように ~
動作時に、膝の内側の違和感が気になったら、足腰のコワバリ箇所や筋肉の不均衡状態をチェックをして、①筋肉の緊張の緩和、②膝関節の可動域の維持、③痛みの緩和などを行い、『変形性膝関節症』の進行を防ぐ事が大事です。
当院は、患者に痛みや無理が無いように、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、脚の筋肉のコワバリの除去や、関節可動域の改善、血液循環の促進を行い、変形性膝関節症の進行抑制と膝の痛みの緩和を行っています。
マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する痛みやしびれなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)