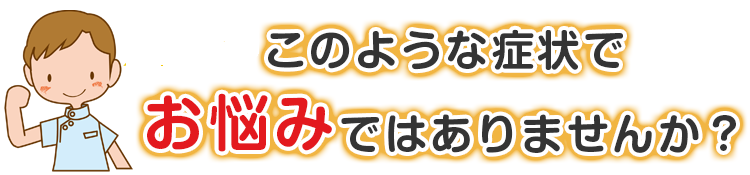看護や介護は、腰を曲げて中腰になったり、身体を支えたりする為に、腰や背中などの“姿勢を維持する筋肉”の負担が大きくなる上に、起床や移動、衣類の着脱、入浴など、一日のさまざまな場面で動作の手助けを行う為に、身体のいろいろな箇所に痛みや不快感が起き易くなります。
これによって、身体の負担が繰り返されると、心や身体に過度な負荷(ストレス)がかかった状態になるので、疲労が大きくなるだけでなく、身体の回復力が低下してくる為に、「疲れが取れない」、「身体が、いつもだるい」、「動くと身体が痛む」といった状態になります。
このような、身体の回復力が追いつかなくなって痛みや疲れが起きてきた場合には、身体の調子(治る力)を取り戻す事が必要なので、身体のコワバリ箇所や血行の悪化箇所を確認して、これらを回復させ、更に、敏感になっている神経を和らげて痛みや不快感を解消し、崩れかかった身体のバランスを整える事が大切です。
【 姿勢を維持する筋肉の、痛みの発生 】
~ 腰痛が起き易く ~
看護や介護をしていると、「身体の向きを変える」、「車いすやベッドへの移動」、「トイレ・入浴の介助」などの為に、患者や要介護者の身体をシッカリと支える必要があるので、どうしても、腰に大きな負担がかかる事が多くなります。
しかも、腰痛が気になって、腰をかばうような姿勢をすると、かえって、腰に不自然な負担がかかってしまうので、余計に腰痛が起き易くなります。
この為、看護や介護は、腰痛やギックリ腰が起き易く、慢性化する事が多いので、「腰痛は、介護職の職業病」と言われます。
~ 肩や背中の筋肉も ~
また、腰痛やギックリ腰以外にも、肩や背中の凝りや痛みなどにも悩まされます。
「抱きかかえる」、「歩行を支える」、「着替えや食事の世話をする」、「入浴を介助する」などの時に、肩や背中の筋肉を使って、シッカリと支える必要があるので、これらの筋肉の疲労や緊張が大きくなると、肩や背中に凝りや痛みが起きるからです。
この結果、介護の仕事をしている人の52.4%~75.0%が、首・肩・背中の凝りや痛みで悩まされ、中でも家で介護している女性の場合は8割以上にもなり、そのうち4割の女性が、絶えず凝りと痛みに悩まされています。
~ 中腰や前かがみ姿勢から ~
これらの痛みが起きる大きな原因は、介護する時の身体への負担が“直接”かかってくる事と、これらの身体への負担が、何度も“繰り返される”為です。
中腰や前かがみになって行う、これらの身体への負担が何度も“繰り返される”と、腰や肩・背中などの“姿勢を維持する筋肉”の緊張や疲労が続いて解消されなくなって、血流やリンパの流れが絶えず悪くなる上に、神経が緊張や疲労に敏感になるので、痛みが起き易くなり、慢性化してくるからです。
更に、何度も上半身の緊張が“繰り返される”と、身体の痛みに加えて、肺や腹部の圧迫が強まるので、「胸からみぞおちあたりに圧迫感がする」、「胸に重たくののしかかる感じがする」、「胸が締め付けられる」、などの違和感や不快感も起きるようになります。
【 広範囲の痛み 】
~ 痛む箇所がハッキリしない ~
看護や介護で身体に疲労が溜まって、身体に痛みを感じる状態になると、痛む場所が「腰あたり…」とか「背中あたり…」と言うように、痛む場所が広範囲に感じられ、しかも、動作によって強まったり、拡散したりします。
これは、疲労が蓄積されると、周辺部分や関連する部分にも、筋肉のコワバリと血流の悪化が生じるので、それらによって神経が刺激されて、広い範囲にわたってニブイ痛みを感じるようになるからです。
しかも、筋肉のコワバリと血流の悪化によって神経が敏感になるだけでなく、疲労や緊張で痛みを抑える働きが弱くなってくるので、疲労や緊張で負荷がかかると痛みが大きくなったり、筋肉のコワバリと血流の悪化で治りづらくなったりします。
~ 筋肉内の硬いシコリから ~
また、看護や介護で疲労が溜まり、血流の悪化と筋肉のコワバリが生じて、コワバリ内に筋肉の硬い“シコリ”ができると、硬い“シコリ”によって血行が遮断されるので、絶えず神経が刺激される状態になります。
これにより“シコリ”から、いつも、神経が圧迫されたような感じや、「うっとうしい」痛みが起きたり、疲労や緊張が増すと、コワバリ感や疼くような痛みが拡がったりします。
この結果、肩や首に“シコリ”ができて神経が敏感になってくると、頭が重くなって思考力が低下する『頭重感』や、頭痛が起き易くなる『頭痛持ち』に悩まされようになったり、あるいは、腰に“シコリ”ができて神経が敏感になってくると、『慢性腰痛』や『ギックリ腰』の原因になったりします。
~ 交感神経の活発化によって ~
更に、腰や肩・背中などの“姿勢を維持する筋肉”に負荷がかかり続けて痛みが生じると、痛む範囲が拡がります。
“姿勢を維持する筋肉”は、他の筋肉よりも神経が多く存在しているので、身体を緊張させる『交感神経』の働きが強まると、それによって交感神経が活発化するので、血管が収縮して血行が悪化し、腰や肩・背中などに、広くコリや痛みが生じたり、慢性的な痛みや不調に繋がったりするからです。
しかも、看護や介護で精神面に緊張やストレスを感じる事が多くなったり、続いたりすると、交感神経が強まって血管を圧迫し、身体の血行が悪くなってくるので、身体全体にダルサや痛みを感じ易くなります。
【 ケアの判断が困難に 】
~ 痛む箇所が特定できない為に ~
痛みは、身体に異常が起きた事を知らせる“アラーム”の役割をしていますが、痛みによる身体からのアラーム信号に気付いても、看護や介護をしていると、途中で休む事ができません。
しかも、痛む箇所が「腰あたり…」とか「背中あたり…」のように、特定できずにハッキリしないと、適切な回復処置がしにくくなります。
この結果、痛みと不快感が続いて慢性化してくると、次第に痛みと不快感が拡がって、身体全体に、痛みと不快感が生じるようになります。
~ 精神的な緊張からも ~
また、介護や看護で、「思い通りにいかない」、「人に頼る事ができない」、「自分の時間を持つ事ができない」などの悩みやストレスを抱えていると、精神的な緊張が強まり、ますます身体の疲労や痛みを感じるようになります。
この結果、「いつも身体が重い、ダルイ」、「慢性的に、肩や腰が痛む」、「眼がショボショボして見えにくい」、「頭痛が治らない」といった事が起きたり、「やる気が起きない」、「鬱陶しくなる」、「集中力が続かない」といった状態になったりします。
更に、「イライラする」、「あまり動いていなくても疲れる」、「考えがまとまらない」、「なかなか寝られない」などが起きると、精神的な疲労が増すので、更に身体の調子を悪化させます。
~ 自律神経のオーバーワーク ~
身体の不調が増したり、身体のリラックス感が失われたりすると、身体の安定を保つ自律神経の働きがオーバーワークになるので、疲労が強まるだけでなく、身体の機能が低下し回復力も低下します。
これにより、身体の機能が低下し、「重くのしかかるような鈍い痛み」、「ズキズキと響く痛み」、「刺すような痛み」、「ヒリヒリするような痛み」、などが起きます。
自律神経がオーバーワークになって体調を保てなくなっているので、湿布薬を貼ったり、お風呂に入ったり、自分でストレッチをしたりしても、痛みや不快感が一時的に緩和されても、続く状態になります。
【 当院の、15分からのマッサージ治療 】
~ 症状の早期発見、早期改善 ~
介護や看護をしていると、肩、背中・腰などの“姿勢を維持する筋肉”に大きな負荷がかかるだけでなく、慢性的な痛みや違和感を引き起こす事もあるので、身体の異常の『早期発見、早期改善』で、体調を保つ事が大切です。
スポーツの世界では、疲労や緊張の『早期発見、早期改善』の効果が分かっているので、運動後にクールダウンを行う事で疲労や緊張を解消し、体調回復を行うようにしています。
この為、当院では、疲労、ダルサ、コワバリなどの解消や、体調不調の改善などを、気が付いた時に気軽にできるように、マッサージ治療を15分から行っています。
~ 15分、30分のマッサージを受けると ~
これは、「マッサージ効果は、時間が長いほうが高い」と思われますが、介護や看護の疲労解消の場合は、“姿勢を維持する筋肉”を、早めに回復させる事が必要なので、1週間に1回でも定期的に受けたほうが改善効果が高いからです。
例えば、朝起きた時や、身体を動かした時などに、重ダルサや痛みを感じたり、身体に動きづらさを感じたりした時に、15分、あるいは、30分のマッサージを受けると、身体に溜まった疲労を解消されるのが実感されます。
疲労や緊張を感じた直後に、短時間でもマッサージを受けると、血行やリンパの流れが早めに回復するので、溜まりかけていた疲労物質が排出され、それによって、ダルサや、つらい筋肉痛が解消されるからです。
~ ツボ治療の併用 ~
また、当院は、ツボ治療を併用したマッサージ治療を行い、痛みや不快感の早期解消だけでなく、体調の改善を行っています。
疲労や緊張によって、疲れ易さや痛みとなって現れてくる箇所が、東洋医学のツボ(経穴)の位置とほぼ一致している事と、ツボが、神経や血管が集まっている箇所なので、疲れ易さや痛みとなって現れているツボに刺激を加えると、その刺激に適応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果がある為です。
この効果によって、筋肉の中を通っている血行が活発化し、それによって栄養や酸素の供給が進み、老廃物を押し流すので、身体の疲労解消の効果だけでなく、身体を休める神経(副交感神経)が働くようになり、体調を保つ自律神経が回復し易くなります。
~ 身体の疲労や緊張などの慢性化には ~
介護や看護による身体の痛みや違和感は、身体の疲労や緊張などの慢性化が影響しているので、体調や気になる症状に合わせて、身体の調子(治る力)を上げていく事が必要です。
当院は、東洋医療をベースにしたマッサージ治療とツボ治療で、疲労箇所を回復させて神経の興奮を鎮め、崩れかかった身体のバランスを整え、慢性的な痛みや違和感の解消を行っています。
マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する疲労やだるさなどの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-1.jpg)