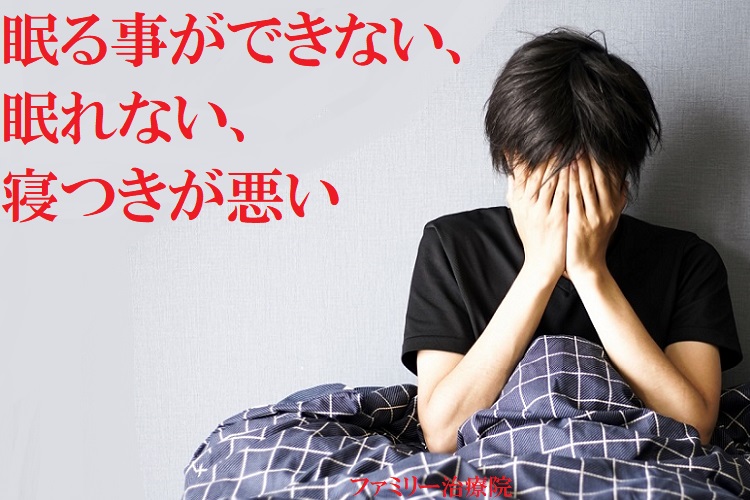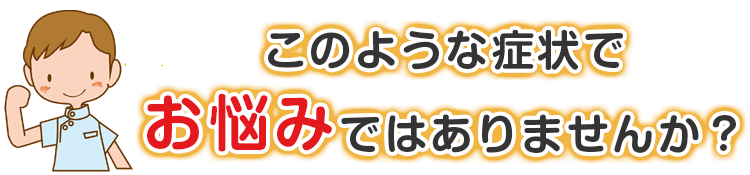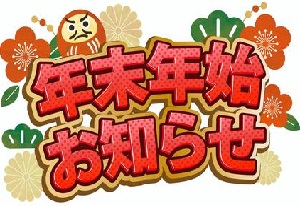疲労や緊張が続いたり、ストレスや悩みを抱えていたりすると、「身体は疲れているのに、なかなか眠る事ができない」、「昼間の緊張感が抜けなくて、眠れない」、「気持ちがイライラして、寝つきが悪い」といった事が起きます。
しかも、眠れない事から、「寝ているのが辛い」、「身体がコワバッテ“寝コリ”を感じる」などが起きると、「気になる事が思い浮かんで、ますます眠れない」、「眠ろうとして、余計に眠れなくなる」などの状態にもなります。
これは、昼間の疲労・緊張・ストレスなどが夜まで続いて、脳の中の“睡眠スイッチ”が入りづらくなっているので、眠る前に脳と身体が“休息状態”になるように、身体の疲労箇所や緊張箇所の確認と緩和を行って、敏感になっている神経を和らげ、眠りにつく前に、身体がリラックスモードに切り替われるようにする事が大切です。
【 脳の中の睡眠スイッチ 】
~ 疲れているのに、寝付けない ~
昼間の気ぜわしい仕事や、忙しい仕事が終わって、疲れて家に帰り、「さあ、寝よう!」とベッドに入っても、気になる事が頭に浮かんで、なかなか寝付けなかったり、眠り着くまでに時間がかかったりする事があります。
このような“眠りたくても、なかなか眠れない”状態になると、眠る為に横になってジッとしているのが辛くなったり、肩や首、背中などの筋肉に痛み(寝コリ)を感じたりして、ますます眠りづらくなります。
この状態が続いてしまうと、朝起きた時に、「気分がスッキリしない」、「熟睡感が無い」、「寝足りなさからボーッとする」などが起き、その日の仕事や活動に支障が生じてしまいます。
~ 睡眠スイッチ ~
このような“なかなか眠れない”原因として多いのが、日中の緊張感や疲労感が夜になっても消えずに残っていたり、心にストレス感が続いていたりすると、脳の中の“睡眠スイッチ”が入りづらくなる事です。
例えば、「眠る時間になっても、仕事の緊張感が抜けない」、「眠ろうとしても、神経が敏感になってイライラする」、「床に就いても、疲労で身体の調子が悪く感じられ、気が休まらない」などがあると、それが精神的な圧迫となって“睡眠スイッチ”が入りづらくなります。
更に、「眠れなければ、明日が困る」とか、「とにかく、眠らなければいけない」という焦りが生じると、眠ろうとする“意気込み”によって、ますます覚醒作用が高まるので、一層“睡眠スイッチ”が入りづらくなります。
~ 不眠症ではなく、寝付きが悪い状態 ~
しかし“なかなか眠れない”状態でも、『不眠症』と診断されるには条件があります。
『不眠症』の診断基準は、「眠ろうとしても、1~2時間以上寝付く事ができないのが、1週間に3回以上、3ヶ月以上続き、これが原因となって、日中に眠気を感じたり、生活に支障が出たりする」と、なっているからです。
この為、寝付くまでに時間がかかる状態であっても、症状がここまで酷くなければ、『不眠症』ではなく、疲労・緊張・ストレスなどが溜まって『寝付きが悪い状態』と判断されることになります。
【 身体のコワバリや血行の悪化から 】
~ 無意識のうちに睡眠状態に ~
このような“なかなか眠れない”状態とは反対に、暖かい布団に入って包まれているうちに、気づかぬうちに『寝落ち』のようにスーッと眠りに落ちてしまう事があります。
これは、暖かい布団に入って、身体がポカポカと気持ちよく感じてくると、身体の表面の血管が拡がって体温が放熱されるので、体内の温度(深部体温)が下がり、これによって脳を含んだ全身の“休息状態”が作り出される為に、無意識のうちに眠りに入ってしまうからです。
簡単に言えば、体内の温度(深部体温)が下がると、生命を支えている体内の反応が不活発になってくるので、身体の機能が低下し、気付かないうちに眠りに落ちてしまうからです。
~ ストレスや疲労感 ~
ところが、仕事や家庭でストレスを抱えていたり、生活に不安や疲れを感じていたりすると、緊張を高める交感神経が活発になり、夜になっても脳の活動モードが続いて、『寝落ち』するような、脳を含んだ全身の“休息状態”が作り出せなくなります。
更に、仕事に対する責任や役割意識を強く感じていると、脳の活動モードが刺激されるので、一層、“睡眠スイッチ”が入りづらくなります。
しかも、仕事をしている時に、無意識に身体に力が入った状態になったり、疲労や緊張で身体の表面の血管が拡がらなくなったりすると、夜になっても緊張モードが残って、体温が放熱しづらくなり、体内の温度(深部体温)が下がらなくなるので、眠ろうとしても、スーッと眠りに落ちる作用が働かなくなります。
~ 首や肩、背中などの痛み ~
これらに加えて、昼間の緊張や疲労で、首から肩、背中、肩甲骨あたりの筋肉がコワバッテいると、神経が圧迫されたり、血行が悪化したりして、神経が刺激されます。
この状態になると、不快感や凝り感で眠りに入りづらくなる上に、「肩のコワバリに体重がかかると痛む」、「首コリや背中の痛みが気になって、ジッと横になっていられない」などが起きて、寝ているのが辛くなります。
しかも、コワバリで背中の神経が敏感になって、肩甲骨の内側からジンジン・ズキズキする痛みを感じるようになると、寝ている時に、背中に上半身の重さがかかって、余計に肩や背中の痛みや違和感が強まったり、気になったりするので、余計に眠れなくなります。
【 最高の睡眠は血流で 】
~ 夜はリラックスモードに ~
本来ならば、人の身体は、一日の疲れをリセットする為に、体調を保つ自律神経の働きによって、日中の活動モードから、夜になるとリラックスモードに切り替わります。
しかし、疲労や緊張が続いたり、ストレスに感じる事が増したりすると、自律神経の中の交感神経の働きが活発化したままになって、筋肉や神経が休まらなくなるので、夜になっても、リラックスモードへ、うまく切り替える事ができなくなって、グッスリと眠る事ができなくなります。
しかも、毎日の疲労・緊張・ストレスなどで、自律神経の交感神経が優位のままになると、覚醒作用が働いて、「眠りたいのに眠れない」状態になったり、血行が悪くなって痛みの感覚が強まり、寝ているのが苦痛になったりします。
~ 身体がリラックスした状態に ~
この為、夜に、心身がリラックスモードに切り替わってグッスリと眠りに付けるには、眠る前に、身体がリラックスできるように心身の疲労や緊張を解いて、身体の血流を良くしておく事が大切です。
この状態になると、身体の表面の血管が拡がって、自然と血流が増すので、『最高の睡眠は、血流で決まる』と言われるように、体内の温度(深部体温)が下がって、脳の中の“睡眠スイッチ”が入り、この結果、自然と寝付き易くなります。
この為、身体の血流を良くして、眠り易くなるように、「寝る前に、ぬるめのお風呂に入る」、「夕方に軽い運動をする」、「寒い時には、湯たんぽで温める」、「暖かい牛乳を飲んでおく」、などが勧められています。
~ 副交感神経が優位に ~
更に、眠る前に、身体を休める副交感神経の働きを高めて、優位にしておく為に、筋肉の柔軟性と弾力性を回復させておく事が大切です。
筋肉が緩むと血管も緩み、身体の血液がスムーズに流れるようになるので、副交感神経が優位になって、心身がリラックスできる状態になり、自然と寝付き易くなるからです。
しかも、夜になって身体を休める副交感神経が優位になると、血圧が低下して、心身がリラックスした穏やかな状態になるので、熟睡感のある眠りができるようになります。
【 当院の、眠り易くする体調改善 】
~ 東洋医療をベースにしたマッサージ治療 ~
このように、眠りにつく前に、脳と身体が“休息状態”になるように、身体の疲労や緊張を緩和して解消する事が必要ですが、毎日の疲労や緊張で筋肉がコワバッテ、血流やリンパ液の流れが悪くなると、夜になって“睡眠スイッチ”が入りづらくなります。
この為、当院は、「眠る事ができない」、「眠れない」、「寝つきが悪い」などで、睡眠に悩んでいる方に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療を行っています。
東洋医療をベースにしたマッサージ治療は、もともと、疲労や緊張などの慢性化による、筋肉由来の凝りや痛みの解消を得意としているので、「寝付きが悪い」場合も、筋肉が凝り固まった箇所を調べて確認し、それらを解消すると、身体の柔軟性や血行が回復し、神経の興奮状態が落ち着いてくるので、“睡眠スイッチ”が入り易くなり、安眠モードにもなるからです。
~ ツボ治療を加えて ~
当院では、これらの効果を高める為に、マッサージ治療にツボ治療を加えています。
ツボは神経や血管が集まっている箇所なので、身体に不調があると、ツボの箇所に痛みや硬さとなって現れ、身体に異常が起きている事を知らせてくれるだけでなく、反応が現れたツボに適切な刺激を与えると、その刺激に順応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があるからです。
この為、ツボ治療で、体調の改善をするだけでなく、身体を休める副交感神経の働きを回復させて、リラックス効果で“睡眠スイッチ”に入り易くさせます。
~ 呼吸筋の柔軟性回復 ~
また、当院では、眠り易くなる為に、呼吸に関係している首・肩・背中の緊張を解消させて、柔軟性の回復を図るようにしています。
疲労や緊張などでストレスを感じていると、筋肉のコワバリが強まったり、交感神経(興奮を高める神経)の働きが高まったりして、呼吸が浅くなり、深い睡眠に入りづらくなるからです。
マッサージ治療で、これらの呼吸筋を緩めて、胸が自然に拡がるようにすると、身体がリラックスしてくるだけでなく、それによって血液やリンパがスムーズに全身を巡るようになるので、脳が眠りにつく為の安眠モードに変わり、眠り易くなります。
~ 体調の改善やリラックス効果 ~
マッサージ治療は、もともと体調の改善やリラックス効果があるので、その効果によって、安眠モードへの切り替えや、質の良い睡眠をもたらす効果があります。
当院は、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、なかなか解消しづらい凝りや疲労を解消し、心身のリラックスを図って、眠り易くなるように体調の改善を行っています。
マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や、不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-5.jpg)