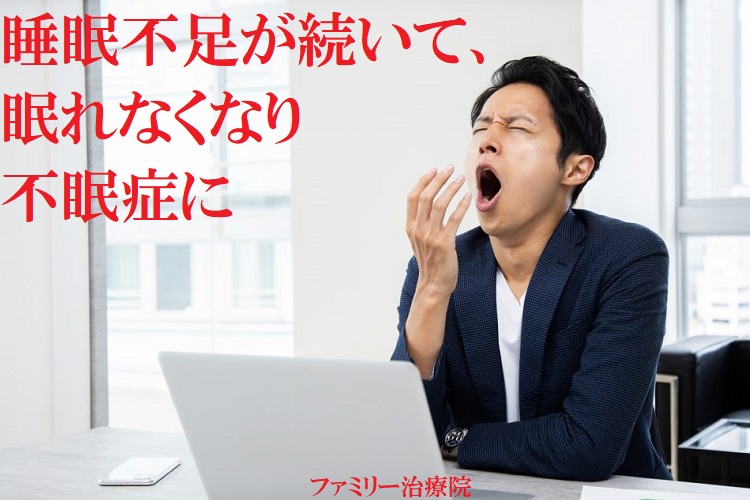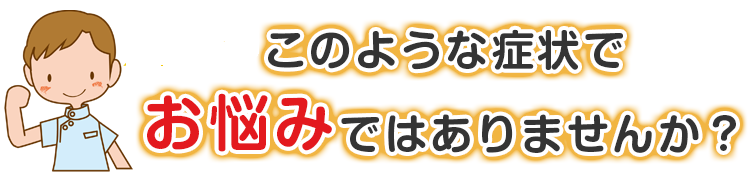仕事や子育てなどで、毎日を忙しく過ごしていると、仕事や子育てに追われて寝る時間を後回しにしてしまうので、「最近、すっかり睡眠不足!」となりがちです。
睡眠不足が続くと、神経を休める事ができなくなるので、感情が高ぶり、「集中力が続かない」、「注意が散漫になる」、「ストレスを感じ易くなる」、「イライラする」などが起き、更に、睡眠不足を解消しようとしても、「疲れているのに、神経が高ぶって眠れない」、「眠っても眠りが浅く、熟睡できない」といった状態になります。
しかも、「身体が一日中だるい」、「頭痛や頭重感がする」などの体調の不調も起きてくるので、睡眠不足が続いている場合は、不眠症の対策と同じように、体調を整えて自然な眠りにつけるように、身体に溜まった疲労や緊張の解消を行って心身を和らげ、“脳が休める”状態にする事が大切です。
【 自覚しづらい睡眠不足 】
~ 睡眠不足の感覚が鈍くなって ~
睡眠不足の状態を続けているうちに、次第に、早く眠ろうとしても眠れなくなり、不眠症と同じような状態になる事があります。
例えば、何かの事情で、夜遅くまで起きていた場合には、翌日に眠気のリバウンドが起きて、頭や身体がヒドク疲れているのを感じ、そして、睡眠不足になっているので眠気も強く感じます。
ところが、毎日、仕事や介護などで追われていると、気持ちが高ぶって、眠気よりも目覚めている力が強くなるので、眠ろうとしても寝つけなかったり、眠りが浅くなって熟睡できなかったり、早いうちに目が覚めてしまったりします。
~ 交感神経の覚醒作用 ~
また、仕事や家事で期待されていたり、反対に、ストレスを強く感じていたりすると、睡眠が不足した状態であっても、眠気を感じなくなって、「短時間睡眠に慣れた」と感じる事もあります。
期待やストレスなどで交感神経が活発に働くと、身体と心が“興奮モード”になって、呼吸、脈拍・血流、消化・呼吸、免疫機能、体温調節などがフル稼働するので、“覚醒作用”が働く上に、夜になっても交感神経の活動がずうっと続く為に“覚醒作用”が働くので、「夜になっても、眠気が来ない」状態になり、朝も「早くから目が覚める」状態になるからです。
この結果、「夜、遅くまで活動できて、朝は、すぐに起きられる」、「毎日5~6時間眠れば、睡眠時間はそれで十分」、「寝つきが良い」、「電車ですぐに眠ってしまうけど、すぐに目覚めるから問題が無い」と感じます。
~ 睡眠不足と不眠症 ~
このように、睡眠不足と不眠症は、「睡眠時間が短い」という事は共通していても、内容的に、全く反対です。
睡眠不足は『眠れるが、眠る時間が足らない』状態なので、眠る事には問題が無く、眠ろうとすれば自然と眠れます。
これに対して、不眠症は『眠ろうとしても、眠れない』状態なので、心身が疲れていても、眠気よりも目覚めている力が強くなります。
【 睡眠不足が続くと 】
~ 睡眠不足を続けてしまうと ~
しかも、睡眠不足が続いても、睡眠不足を続けてしまう理由として、「休みの日に寝ればいい」とか「まだ大丈夫だろう」と睡眠不足を軽く考えたり、寝る間を惜しんで勉強や仕事をする事を“美徳”と考えたりする事があります。
しかし、これによって睡眠不足の状態を続けると、脳の中の、睡眠に切り替わる仕組みや、睡眠を維持する仕組みがキチンと働かくなります。
この結果、睡眠不足を自覚しづらくなって「短時間の睡眠に慣れた」と思いますが、睡眠不足を続けているうちに、眠気よりも目覚めている力が強くなり、寝ようとしても眠れなくなります。
~ 短時間睡眠に慣れたと思っても ~
また、睡眠時間が短くなると、深い眠りが妨げられる事があります。
睡眠時間が短くなって、日中の疲労・緊張やストレスなどが解消されづらくなり、蓄積されてくると、脳に蓄積された老廃物の除去や、熟睡に必要な成長ホルモンの分泌などが十分に分泌されなくなり、夜になっても神経の興奮が鎮まらなくなり、夢を見るレム睡眠と大脳を休めるノンレム睡眠のリズムが崩れるからです。
更に、仕事や家事の時間を最優先にして睡眠時間が短くなると、自律神経の交感神経の働きが強まり、身体を休める副交感神経の働きが弱まるので“浅い眠り”になり、グッスリと質の良い睡眠がとれなくなったり、疲労した脳や身体を休ませる事や回復させる事ができなくなったりします。
~ 寝落ち ~
また、「毎日5~6時間眠れば、睡眠時間はそれで十分」、「寝つきが良い」と思っていても、睡眠時間が不足している為に、布団に入ると、意識が急にシャットダウンして無くなってしまい、“寝落ち”になっている事があります。
“寝落ち”は、「眠りに入る」よりも、失神に近い状態なので、睡眠の質が低下して、深い眠りに入れなくなります。
この結果、“寝落ち”を繰り返す状態になると、脳をしっかり休ませる事や、疲労を回復させる事が十分にできなくなるので、「疲れがなかなか抜けない」、「肩こり」、「頭痛」といったさまざまな身体の不調に繋がります。
【 寝だめ、寝具の買い替え 】
~ 寝だめ ~
この結果、睡眠不足を繰り返していると、「朝、起きた時に、熟睡感がなくスッキリしない」、「昼間、眠くなる」、「頭がボーッとする」などを感じ、その上、脳の疲労が続く為に、毎日、「ダルイ」、「頭が重い」、「頭痛がする」、「身体に疲れを強く感じる」などに悩まされます。
このような状態になると、「睡眠不足が原因になっているので、休みの日に“寝だめ”をすれば、睡眠不足を解消できる」と思いますが、睡眠不足が何日も続くと、疲労が心身に蓄積して、疲労の回復が追い付かなくなるので、1日~2日ゆっくり休んでも、疲労が解消できなくなります。
しかも、睡眠不足が習慣化すると、それに合わせて、身体の中に『体内時計』や『覚醒のリズム』ができるので、睡眠不足の解消の為に睡眠時間を確保しても、「なかなか眠りにつけない」とか、「眠りが浅くて、目が覚めてしまう」、「疲労しているのに、熟睡できない」などが起きます。
~ 寝具の買い替え ~
更に、睡眠不足が毎日続いて、心身の疲労や緊張が解消されなくなると、枕の高さが気になったり、寝苦しさを感じたりします。
これは、身体の筋肉のコワバリが強まったり、血行の悪化で神経が敏感になったりするので、枕の高さが合わなく感じたり、呼吸運動が制限されて胸に圧迫感を生じたりするからです。
この為、気になる枕や布団・マットレスなどを買い替えても、原因が寝具ではないので、やはり、寝ている最中に、依然と同じように、枕の高さや寝苦しさを感じます。
~ 眠りたいのに、眠れない ~
このように睡眠不足が続くと、「夜寝つきが悪い」、「眠りを維持できない」、「朝早く目が覚める」、「眠りが浅く十分眠った感じがしない」などが強まり、不眠症と同じような『眠ろうとしても、眠れない』状態になります。
また、「集中力・記憶力・注意力の低下」、「イライラや焦り」、「やる気が出ない」などに悩まされたり、体調を維持する自律神経の働きが低下するので、「疲労感が続く」、「身体がだるい」、「頭痛がする」、「胃腸の違和感」なども起きたりします。
病院では、睡眠不足が続いて眠れなくなっているので、個人個人の睡眠不足の原因を特定して改善する『非薬物療法』によって、2~4か月ぐらいの期間をかけて治療したり、短い治療期間でも1ヶ月半~2ヶ月ぐらいをかけて治療したりします。
【 当院の、睡眠不足の解消治療 】
~ 慢性的な身体の疲労や緊張の解消から ~
当院では、睡眠不足の解消や体調の改善に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、慢性化した疲労や緊張を回復させて体調を整え、“脳が休める”ようにしています。
「疲れがとれない」、「すっきり起きられない」などが起きた場合には、まずは、慢性的な身体の疲労や緊張を解消させて、身体や心がリラックスできるようにして、それにより、自然な眠りにつけるようにする事が必要になるからです。
東洋医療をベースにしたマッサージ治療は、昔から、身体の疲労や緊張の解消だけでなく、身体を休める効果も認められて利用されてきたので、この効果を使って、自然な眠りにつけるようにしています。
~ 後頭部の筋肉がコワバリ ~
特に、睡眠不足が続くと、疲労と緊張で首や後頭部の筋肉がコワバッテくるので、血行が悪化して神経が敏感になり、脳の疲労が回復しづらくなります。
この為、首や後頭部のコワバリ箇所を確認して、マッサージ治療で解消して回復させると、脳への血流が改善し、脳の疲労解消に、かなり効果があります。
更に、寝ている時の、肩や背中のコワバリ感や、呼吸の息苦しさを無くす為に、肩や背中のコワバリを解消すると、上半身の柔軟性が回復して、自然に寝返りができるようになり、身体のコワバリ感や息苦しさも解消されます。
~ ツボ治療の利用 ~
当院では、このような体調の改善に、マッサージ治療にツボ治療を加えて、筋肉の緊張解消や、滞った血液やリンパ液の流れを回復させて、神経の興奮を鎮め、自然な眠りにつけるようにしています。
ツボが、身体の不調時に、反応点として、身体の異常を知らせる箇所でもあり、症状を改善する箇所でもあるので、反応が現れたツボに適切な刺激を与えると、その刺激に順応して、痛みや違和感が減少したり、筋肉内の血流が改善したりする効果があるからです。
この効果から、身体の疲労箇所や緊張箇所を確認して、ツボ治療を加えて解消させていくと、身体の緊張が緩み、身体がリラックスしてくるようになり、眠り易くなります。
~ 東洋医療をベースにしたマッサージ治療 ~
東洋医療をベースにしたマッサージ治療は、身体の「ダルサ」、「肩凝り」、「疲れ易さ」、「食欲低下」、「イライラ」」などを和らげ、心身をリラックスさせる効果があります。
当院は、睡眠不足の解消治療や体調の改善に、東洋医療をベースにしたマッサージ治療で、首、肩、腰、疲労などの不調を解消させて、心身の調子を整え、“脳が休める”ようにしています。
マッサージの施術時間は、15分からです。 関連する身体の不調や、不快感などの症状の、ご相談は、[メール]、または[電話]で、お受けしています。マッサージ専門【ファミリー治療院】-4.jpg)